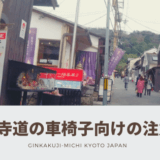こんにちは!
みなさんは、
京都の太秦はご存知ですか?
まず、
太秦ってなんて読むねん!
と言うツッコミが出てきそうですが、
「太秦=うずまさ」
と読みます。
太秦(=うずまさ)は、
京都市中心部より少し西寄りのこのエリアです。
5世紀頃にこの辺りを治めていた豪族、
「秦氏」が関係しています。

京都にいた秦氏(イメージ)
今回は、
太秦という地名がなぜできたのかということと、
太秦周辺のオススメの神社仏閣をご紹介します!
太秦は、
豪族、秦氏が関係してい流のですが、
結論から言うと、
太秦=うず(太)高く秦氏が絹を積んで天皇に献上した
これが太秦(=太秦)の名前の由来です。
1:秦氏は、朝鮮半島からの渡来者。太秦の読み方の由来は絹の献上
①「太秦」の読みの由来となった秦氏が桂川流域は、多数の集落の遺跡が発見されている
太秦(=うずまさ)の読み方の名前の由来となった秦氏は、
京都市の西部を流れる
桂川流域と、東の深草周辺の鴨川に進出しました。
桂川といえば、
有名なのは、
嵐山の渡月橋ですね。

嵐山の渡月橋
太秦の名前の由来となった秦氏の治めた
桂川周辺には、
旧石器時代から縄文時代、弥生時代にかけて
多くの石器や集落の遺跡が発見されています。
京都の盆地の地形を生かした生活が、
縄文時代から行われていたとは驚きです。
②太秦を作った秦氏は、5世紀に入った頃に桂川流域を主に開拓した
その後、
5世紀に入ると、
京都盆地には、多くの移住者たちが進出しました。
その多くは、
列島の人々以外にも、多くの渡来人を含みます。
その一人が、
太秦の街開発を行った「秦氏」です。

京都で太秦を作った秦氏(イメージ)
太秦(=うずまさ)の名前の由来となった秦氏のような渡来人たちは、
先進的な技術によって京都盆地を開拓しました。
特に太秦(=うずまさ)の名前の由来となった秦氏は、
西部の桂川周辺を土木技術によって開発しました。
その時に同時に養蚕や機織技術を広め、
太秦周辺を豊かな産業地帯に変えました。
聖徳太子の側近として働いていた秦氏は、
そこで作られていた絹を朝廷を納めた際、
「うず(太)高く、秦氏が絹を積んで献上した」
ということで、
太秦(=うずまさ)
という読み方の地名ができたと言われています。
2:名前の読み方の由来となった秦氏の治めた、太秦エリアで楽しめる京都観光
①太秦エリアから北へすぐ。世界遺産・仁和寺
秦氏が納めていた太秦エリアは、
現在でも多くの撮影が行われている、
「太秦映画村」が有名です。
映画村もオススメですが、
その他にもオススメな太秦周辺の世界遺産のお寺がありますので
ご紹介していきます。
まず最初は、
「世界遺産・仁和寺」

京都の世界遺産・仁和寺
こちらは、
背の低い桜、
「御室桜」で有名な世界遺産のお寺です。

京都の世界遺産・仁和寺の御室桜
御室仁和寺は、
春だけでなく、
年中楽しめます。
特に、
こちらの
「仁和寺宸殿」

仁和寺の庭園
こちらのお庭から眺める五重塔は僕自身もお気に入りです。
②仁和寺の隣の世界遺産、太秦からも近い、龍安寺
秦氏の納めていた、太秦(=うずまさ)周辺のオススメスポット。
続いては、
「龍安寺」です。

京都の世界遺産・龍安寺
こちらは、
先ほどご紹介した世界遺産、仁和寺のすぐ隣にあり
歩いていくことができます。
一番の見どころは、
石が15個ある庭園(=方丈庭園)です。

世界遺産・龍安寺の石庭
龍安寺のこちらの方丈庭園は、
石が15個配置されています。
この石は、
一度に同時に見れないように設計されているそうですが、
人によっては見える人もいるそうです。
ぜひチェックしに拝観してみてください!
③秦氏が治めた太秦、読み方と歴史を知っておくとさらに面白い
今回ご紹介した太秦(=うずまさ)、
秦氏が治めていた時に、
天皇に献上した絹の多さがと地名となるという歴史、
その周辺のお寺についてご紹介してきました。
太秦(=うずまさ)は、普通に読んだら、読める人は少ないはず。
「京都の難解地名」としてもよく出てくると地名です。
ですが、
その太秦(=うずまさ)の名前の由来、歴史背景を知ると、
すぐに覚えられますね。

京都にいた秦氏(イメージ)
このように京都の歴史は知れば知るほど奥が深いです。
また色々と調べてご紹介していきたいと思います!
ここまで読んでいただきありがとうございました。
それではまた!