こんにちは!
今回ご紹介する、
「京都検定で欠かせない知識」
は、
京都のお正月で知っておきたい知識
です。
日本料理の発展した京都では、
独特のお正月文化もあります。

京都・清水寺
今回ご紹介するのは、
以下の4つです。
⑴京都のお正月、お雑煮は白味噌を使い、縁起物の京野菜を入れる
⑵お正月のおせち料理には、カズノコ・たたきごぼう・ごまめが京都では、欠かせない
⑶お正月の3が日に使う焼き鯛は、京都では「にらみ鯛」という呼ぶ
⑷祝箸に京都では、お正月用に柳箸を使う
京都をよく知るという方にとっては、
常識的な内容となっていますので、
新鮮味がないかもしれませんが、
京都検定で抑えておきたいお正月の知識を知りたい!
という方は、
是非最後まで読んでみてください!
「京都観光・文化検定試験 公式ガイドブック」
【3級向けにさくっと勉強したい方はこちら!】
1:京都のお正月で使われる野菜たち、京野菜のオンパレード
①お雑煮は白味噌、具材には縁起物を使う京都のお正月
京都のお正月のお雑煮には、
「白味噌を使う」
このことは、
京都に詳しくない方でもご存知の方は多いかもしれません。
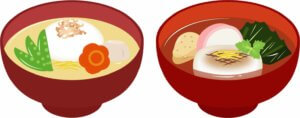
また京都のお正月で使われるお雑煮の具材は、
丸いものに調え、縁起物で統一
されていて、
出世の願いを込めた「頭芋」
根を張る「雑煮大根」
子孫繁栄の「小芋」
大きな芽の出る「クワイ」
などが用いられます。
②京都のお正月のおせち料理には、この3種が欠かせない
お正月といえば
「おせち料理」

京都のお正月でも、
もちろんおせち料理は食べられるのですが、
京都のおせち料理で
「欠かせない3種」
があるのはご存知ですか?
その3種とは、
それぞれのリンクからレシピに飛びます
これらが京都のお正月のおせち料理で欠かせない3種です。
カズノコは、卵の数が多いことから
「子孫繁栄」
たたきごぼうは、
「地に根を下ろすように」
という願いが込められ、
ごまめを利用した田作りは、
「豊作」
を祈って食べられます。
京都検定でも出題されていますので、
おさえておきましょう!
2:焼き鯛やお箸もちょっと違う、京都のお正月料理
①京都のお正月の焼き鯛「にらみ鯛」に、お箸をつけてはならない
お正月料理では、
「焼き鯛」
も欠かせませんよね!

お正月で欠かせない焼き鯛
京都では、
お正月に食される焼き鯛のことを
「にらみ鯛」
と呼び、
お正月の3が日はお箸をつけない
という習慣があります。
食事の度に、
食前にあげられますが、
誰もお箸をつけることなく下げられます。

そしてまた出てきては下げられるというのを繰り返し、
4日以降に、
電子レンジで温められて食べられます。
②祝い箸には柳箸、京都のお正月で使うお箸は、両箸が削られている
ここまで
京都のお正月の料理や食材についてご紹介してきましたが、
最後にご紹介するのは、
「京都のお正月で使われるお箸」
です。
京都のお正月では、
「柳箸」
と呼ばれる、
両箸が細く削られたお箸が使われます。

京都のお正月に使われる「柳箸」
柳箸は、
「祝い箸」「両口箸」「はらみ箸」とも呼ばれ、
長さは約24センチです。
柳は、香りもよく折れにくいことから
縁起の良い木とされています。
両箸が削られているのは、
「片方は自分で使い、反対側は神様が使う」
とされていますが、
柳箸の反対側を使うことは決してありません。
(取り箸としても使いません)

京都のお正月に欠かせない、柳箸
今回ご紹介してきた
「京都のお正月で欠かせない知識4つ」
さらに詳しく知りたいという方は、
「京都観光・文化検定試験 公式ガイドブック」
を見れば、
京都についてさらに詳しくなれます。
気になる方や、
京都検定の受験を目指している方は、
是非一度手に取ってみてください!
【3級向けにさくっと勉強したい方はこちら!】
ここまで読んでいただきありがとうございました!
それではまた!



