こんにちは!
京都の野菜といえば京野菜。
様々な京都発祥のブランドの野菜があります。

50種類近くある京野菜たち
それらの京都の野菜は、
何故あんなに種類が多く発展したのか。
その理由は以下の2つです。
①京都市内は海が遠く、野菜を作る必要性があった
②京都特有の盆地の気候が、今日野菜の発育に適していた
京野菜には、
「京の伝統野菜」
と
「ブランド京野菜」
という2つの種類があります。

京野菜・水菜
「京の伝統野菜」は、
現存するものは38種類(絶滅したものを含めると40種類)で、
1987年に京都府によって定められた基準を満たす京野菜たちです。
一方、
「ブランド京野菜」は、
京都府の外郭団体である、
「公益社団法人京のふるさと産品協会」
が保証したもので、
「京マーク」が貼られます。
今回は、
京野菜の発展の理由、
京野菜の種類についてご紹介していきます!
1:京野菜が生まれた頃の京都は、大都市で食べ物が必要だった地形と気候を生かした野菜づくり
①海が遠い地形を逆手にとって野菜を開発
平安京時代の京都は、
人やモノ、情報が集まる
国内最大の都市でした。

その人口は、
世界有数の大都市にも匹敵するほど。
ですが、
京都市内は、
京都府の南部に位置していることから
海から遠く、
海産物の仕入れは困難を極めていました。
そんな地形により、
朝廷や都の人々の生活を守り、
生活を賄うためには、
野菜づくりは
重要課題でした。
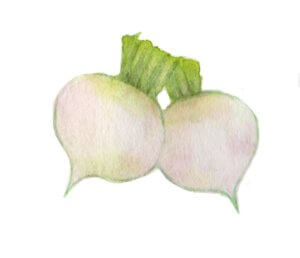
京野菜・聖護院かぶ
②盆地の気候は、京野菜の発育に最適だった
また京都市内は、
清少納言が歌の中でも
「京都の冬は寒く、夏は暑い」
と言っていたほど
1000年前から京都は住みにくい土地柄でした。
ですが、
四季の移り変わりもはっきりしていて、
日中と夜の気温差がある京都は、
野菜作りには最適の気候でした。
また、
盆地である京都には、
水も溜まりやすく
北山・東山・西山の三宝から流れ出してきた
肥沃な土壌も
京野菜の発展に貢献したそうです。

2:京都のそれぞれの地で根付いた京野菜たちは農家の努力の賜物
①伏見で生まれた今日野菜の代表格「九条ねぎ」
ここからは、
少し京野菜をご紹介。
まずは、
「九条ねぎ」

京野菜・九条ねぎ
今や日本人なら誰もが知っているであろう京野菜の一つです。
伏見稲荷大社が創建された頃に京都に導入されたネギが
「九条ねぎ」となりました。
元々は、
甘くて風味の良い青ネギで
内部に滑りが多いのが特徴です。
魚の臭みを消したり、
体を温め、消化を助ける効果もあります。
料理としては、鍋物に多く使われます。
九条ねぎは、
「京都の伝統野菜」でもあり、
「ブランド京野菜」でもあります。
②近江からきた聖護院かぶは、
2つ目は、
「聖護院かぶ」
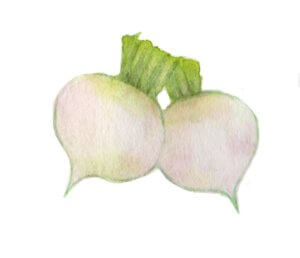
京野菜・聖護院かぶ
千枚漬けの材料としてもよく使われる聖護院かぶ。
淡白な味わいなので
鯛のあらや、ブリのあらなどの
脂の乗った魚との相性もバッチリです。

京野菜・聖護院かぶを使った千枚漬け
聖護院かぶも
「京都の伝統野菜」でもあり、
「ブランド京野菜」でもあります。
③農家の努力が、京野菜のブランドを生んだ
2つのブランドを合わせると、
約50種類にもなる
「京野菜」

これらは、
京都の独特の気候と地形を生かして
篤農家(=研究・奨励に熱心な農家)たちの
努力と工夫によって、
味はもちろん、
栄養価の高い京野菜を作り出したと言われています。
日本料理=京料理
と言われるのも納得です。

京料理
今回は
京野菜についてご紹介してきました。
京都で野菜が発展したのは、
①京都市内は海が遠く、野菜を作る必要性があった
②京都特有の盆地の気候が、今日野菜の発育に適していた
これらに加え、
農家の努力の賜物もあったことは間違いなさそうです。

京都の農家の活躍なくして京野菜の発展はなかった!
ここまで読んでいただきありがとうございました!
それではまた!



