こんにちは!
京都観光では、
必ずお寺や神社のの一つや二つは訪れると思います。

京都の世界遺産の国宝建築
東寺の五重塔
金閣寺や清水寺などを始め、
一生あっても通い切れないほどの
神社仏閣があります。
そんな京都には、
いくつの国宝の建築物があるかご存知ですか?

京都の国宝建築の一つ、東寺の五重塔
その数は、
72棟で、京都が日本一です。
国宝の建築物の棟数
1位:京都(72棟)
2位:奈良(71棟)
3位:滋賀(23棟)
4位:兵庫(14棟)
京都の国宝建築の大半は、
京都市内、及びその周辺にあります。
その京都の国宝建築の歴史についてご紹介します!
1:平安時代に始まった、京都の神社仏閣建築
①72棟ある、京都府下の国宝建築
京都の国宝建築の棟数は、
72棟で日本一です。
京都の町は、
古代の平安京に始まり、
中世都市へと変わっていきました。
近世の諸島には、
豊臣秀吉による都市改造によって江戸や大坂と並ぶ、
三都として発展。

京都の国宝建築・二条城
「京都の町屋についてはこちらから」
現在も多く残る、
京都の神社仏閣の国宝建築物が、
その歴史を物語っています。
②平安時代の京都には浄土信仰の建築がはやった
奈良時代の以前に大陸から導入された寺院建築は、
土間と瓦屋根を特徴とする
「中国式の建築」で
建物の内部は、
仏像を安置する場所として使われました。
平安時代に入ると、
内部空間(礼堂)が
僧侶の礼拝のために加えられ、
仏像を安置する内陣と
高い床を貼った中陣・外陣が作られました。
また、
密教の流行とともに、
境内が山地に設営されました。

山地に境内のある、京都の世界遺産の国宝建築・清水寺
清水寺は密教ではありませんが、
山地伽藍などの特徴が平安時代のものとして知られています。
また平安時代には、
浄土信仰の流行もあり、
その風景を模した、
建築と庭園の組み合わせである
「園(苑)池式寺院」
が藤原道長などによって作られました。

平安時代の国宝建築、平等院
平安時代の京都の国宝建築としては、
世界遺産の平等院鳳凰堂などが、有名です。
2:戦国時代を経て、現代に残る京都の建築
①応仁・文明の乱でわずかに残った京都の建築
応仁・文明の乱によって
京都の市街地は広範囲に焼け野原となりました。

そのため古い現存する寺院建築は少ないですが、
蓮華王院(三十三間堂)など、
瓦屋根ではなく檜皮葺(ひわだぶき)の屋根になるなど
和風化した建築の姿もみられ始めました。

和風化した京都の国宝建築の三十三間堂
②中世から広まった「禅宗様」の京都建築
中世には、
「大仏様」「禅宗様」の建築が大陸から伝えられます。
大仏様が取り入れられた例は、
京都では少ないですが、
東福寺の山門などは、
その珍しい事例の一つです。
「禅宗様」の京都の国宝建築の特徴は、
禅宗寺院に限らず、
京都の多くの寺院建築に取り入れられました。
戦国時代以降は、
豊臣家や徳川家によって、
東寺や知恩院、
清水寺など
多くの寺院が復興され、
現代に歴史を繋いでいます。

京都の知恩院
この時代の建築は、
現代に伝えられているものも多く、
重要文化財に指定されている京都の寺院建築の多くが
その時代のもので占められています。
3:国宝建築で、京都に歴史を学ぶ
①京都の国宝建築を知れば、観光が楽しくなる
今回は、
京都の国宝建築の歴史についてご紹介してきました。
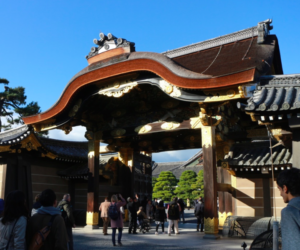
京都の世界遺産の1つ、二条城の唐門
京都の国宝建築を知れば、
京都を訪れた際の観光も楽しくなること間違いなしです。
歴史背景によって形式の異なる、
京都の国宝建築。

京都の国宝建築、北野天満宮の本殿
現存するものも多いのが京都の国宝建築の特徴です。
ちょっとした京都観光の豆知識として
皆さんのお役に立てば嬉しいです!

京都の国宝建築の清水寺
ここまで読んでいただきありがとうございました!
それではまた!



