こんにちは!
今回ご紹介したい京都の豆知識は、
「五山の送り火」
についてです。

京都の五山の送り火
毎年8月16日に行われるこの行事は、
京都の夏の風物詩の一つです。
そんな五山の送り火についてご紹介していきます!
1:20分で6つの文字。五山の送り火は京都の夏の風物詩
①夜8寺に始まり、5分間隔で次々点火
毎年8月16日に行われる、
京都の「五山の送り火」

五山の送り火
東山の如意ケ岳の支峰大文字山の
「大の文字」から始まります。
京都では先祖の霊を鴨川に流す習慣があり、
五山の送り火もまた、
先祖の霊を供養し、
あの世に送るための行事です。
②五山の送り火の起源は、室町時代
五山の送り火の起源は、
「万灯篭」や「千灯篭」などと呼ばれる
灯篭行事だと言われています。
五山の送り火の起源は、
室町時代以降に、
京都と周辺地域で行われてきたとされています。
あの世から戻ってきた先祖を供養し、
日に照らしてお帰りいただくという、
お盆に行われる、特徴的な行事です。

当初は、素朴な行事であったが、
大勢の人たちに見せるために風流化したのが万灯篭で
さらに大勢の人たちに見せるために工夫されたのが、
五山の送り火になったと考えられています。
現在のように、
夏の恒例行事として定着したのは、
江戸時代の初期ごろです。
2:五山の送り火で表現される文字6種類
①6つの山に5つの文字
五山の送り火は、
6つの山で行われます。
それぞれの文字は以下の通りです。
「大文字山」:大
「松ヶ崎西山」:妙
「東山」:法
「西賀茂船山」:船
「大北山の大文字山」:大
「嵯峨鳥居本の曼荼羅山」:鳥居形
大文字山から始まり、
5分間隔で
それぞれの文字が点火されます。
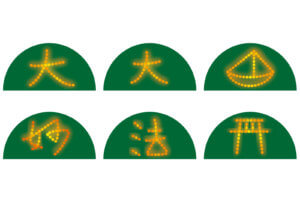
五山の送り火で表される文字
明治時代までは、
「い」の文字や
「竹の先に鈴」
など他の送り火も存在していました。
大勢の人に見てもらうために、
山の斜面に火床を築き、
そこに松明で大きな文字や様々な図柄を描く
という発想が生み出されて完成しました。
②五山の送り火の「大文字」の意味は、宇宙を表す
五山の送り火で最も有名な文字と言っても過言ではない、
「大」の文字。
その字形には様々な説があります。
弘法大師空海がはじめたとされる説、
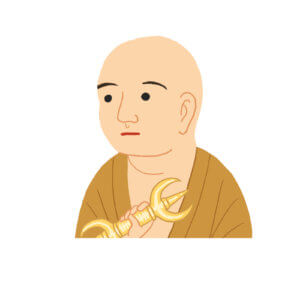
空海
室町幕府8代将軍足利義政が、
子供である義尚の冥福を祈って定めたとされる説。
いろいろな説がありますが、
「大」の文字の意味としては、
中国の古代仏教思想である
「五大」に由来するものとも考えられています。
「五大」とは、
宇宙を構成している主要な5つの要素
「地・水・火・風・空」を指します。
3:五山の送り火で京都の夏を感じる
①詳しく知ると楽しい京都の五山の送り火
お盆に帰ってきたご先祖様をもてなし、
あの世に送り返すための行事とされている
京都の五山の送り火。

京都の五山の送り火
夏の京都の風物詩として
多くの人に見てもらうための工夫が
今の形になっています。
いつまでも続く京都の伝統行事として、
これからも楽しめたらと思います!
ここまで読んでいただきありがとうございました!
それではまた!



